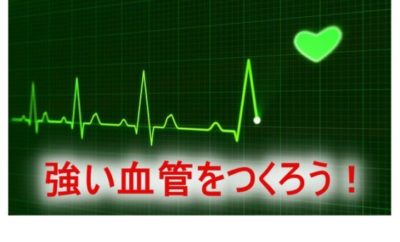お元気ですか? 苺です!
苺(いちご)と書いて苺(まい)と読みます。


食中毒ってふせげるのかなぁ~?

食中毒には原因があるから、正しい知識があればほとんどが防げるよ!
食中毒といっても種類がけっこうあります。
夏に多そうなイメージですが、冬の食中毒もあなどれません。
食中毒にかかってしまうと体調不良でいっきに老けてしまいますので、しっかり予防しましょう。
食中毒は、ちょっとした知識で防げますよ。
◎食中毒の種類
細菌性食中毒(6~9月に発生しやすい)
感染型:サルモネラ属菌・腸炎ビブリオ・病原性大腸菌・ウェルシュ菌・カンピロバクターなど
毒素型:黄色ブドウ球菌・ボツリヌス菌・など
ウイルス性食中毒(冬に発生しやすい)
ノロウイルス・A型肝炎ウイルスなど
寄生虫食中毒
アニサキス・クドア・サルコシスティスなど
化学性食中毒
水銀・ヒ素・ヒスタミンなど
自然毒食中毒
動物性:ふぐ毒・貝毒など
植物性:毒キノコ・ジャガイモの芽など
◎食中毒菌の種類
サルモネラ菌
哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類などの体内に生息しています。
とくに牛・豚・鶏は常に保菌しているので、卵・肉の生食には注意が必要です。(肉さし・卵かけごはん)
「乾燥に強く、熱に弱い」のが特徴ですので、じゅうぶん加熱すれば問題はありません。
生の肉を切ったまな板にサルモネラ菌がついていて、そのまま野菜などを切って菌が付着することがあります。
まな板を使い分けたり、包丁を熱湯消毒することも重要です。
ペットなど動物をさわった後はしっかり手をあらいましょう。
症状:吐き気・嘔吐 ➡ 腹痛・下痢・発熱・頭痛
腸炎ビブリオ
海水や海中に常在して、海水温度が20℃以上になると増加しはじめます。
魚介類に付着することが多いため、未加熱の魚介類を食べたあとに強い下痢・嘔吐の症状がでた場合は、腸炎ビブリオの疑いがあります。
傷口から感染する場合があるので、キズがある状態で海水浴をした時も感染する可能性はあります。
真水では生きられないため、新鮮な魚介類でも水道水などでよく洗浄する事をおすすめします。
加熱処理をすれば確実に死滅します。
4℃以下ではほとんど繁殖しないので、刺身などは氷・保冷剤で低温を維持するよう心がけましょう。
魚を切ったまな板から感染することがありますので、まな板の殺菌・洗浄をじゅうぶんに行ったり、まな板の使い分けをするようにしましょう。
下痢・嘔吐・発熱 ➡ しびれ・チアノーゼ
病原性大腸菌(O-157)
病原性大腸菌は種類が多く、すべてが危険というわけではありません。
が、O-157のようなベロ毒素をだすタイプが要注意です。
ベロ毒素をだすのは他にもO-26・O-111があります。
O-157のやっかいなところは、少数の菌でも発症する事です。
熱には弱いので、じゅうぶんに熱処理して、なまもの・日にちのたったものは極力さけましょう。
3~5日の潜伏期間があります。
下痢 ➡ 腹痛・血便
ノロウイルス
11~1月に多く、感染すると12~48時間の潜伏期間を経て発症します。
発熱・腹痛・下痢・嘔吐
嘔吐を繰り返すので、脱水症状に気をつけましょう。
原因となる食品は生牡蠣やよく火をとおしていない貝が考えられますが、2次感染が大多数をしめます。
感染者の吐しゃ物や便を処理する時は、エプロン・マスク・手袋などを着用し、すみやかに処理しましょう。
ノロウイルスは普通のアルコールでは死滅しません。
アニサキス
魚介類につく寄生虫ですので、刺身に注意しましょう。
もともと内臓に寄生していますが、鮮度が落ちると内臓から身に移動します。
魚を丸ごと購入する時は、新鮮なものを選び、すぐに内臓を取り除きましょう。
みぞおちの激しい痛み・嘔吐