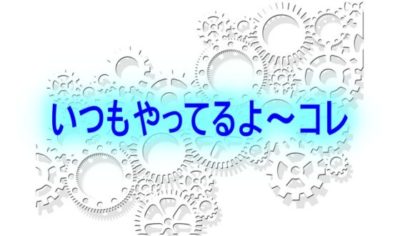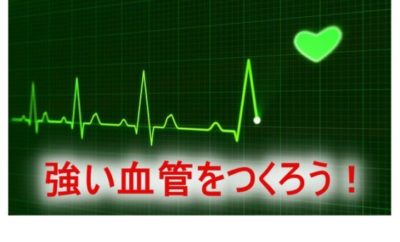お元気ですか? 苺です!
苺(いちご)と書いて苺(まい)と読みます。


食中毒対策って言ってもさ~
見えないんだから、手ごたえがないよね~

でもいろんな菌のいろんな特性を頭に入れておけば、自信をもって対策できるよ!
菌にはどんな種類があるのでしょう?
食中毒をもたらす菌
腸管出血性大腸菌(O-157)
むずかしい名前ですが、O-157やO-111の名で知られています。
気温の上昇によりふえるので、夏場はとくに危険です。
牛や羊の腸管にいる菌ですので、牛の生肉にはとくに注意しましょう。
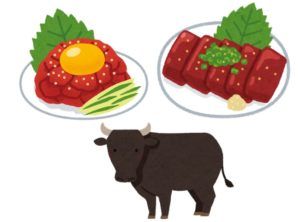
牛レバーの生食やユッケは、鮮度や保存法に安心できるものを選ばないといけません。
またハンバーグやサイコロステーキは、しっかり火をとおすことが鉄則です。
乾燥に強くて野菜にもついていることがあるので、流水でじゅうぶんに洗い75℃以上にお湯に1分以上つけて退治しましょう。
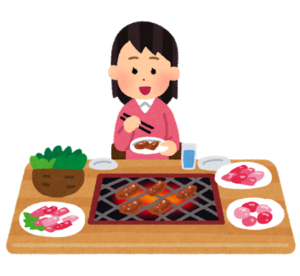
サルモネラ
サルモネラ菌は「卵に注意!」とよくいわれます。
卵かけごはんや親子どんぶり・オムライスなど、生や半熟の卵料理には新鮮な卵を使用しましょう。
また自家製のマヨネーズやカスタードクリームを作る時も、新鮮卵をえらびましょう。
さらに卵だけでなく、牛・豚・鶏の腸にすみつくので加熱不足の肉にも注意が必要です。
卵も肉も75℃以上で1分以上加熱すればOKです。

カンピロバクター
牛・豚・鶏などの腸にすみついている細菌で、とくに鶏には高い確率で発生しています。
ですので鳥刺し・たたき・鶏レバー生食などはさけましょう。
ただし食肉の中心部まで、75℃以上で1分以上加熱すればOKです。
![]()
この菌で食中毒をおこすと、あとでギランバレー症候群を発症するという関係性が指摘されていますので、おぼえておきましょう。
ウェルシュ菌
この菌は、いままでのものとちょっとちがいます。
カレー・シチューが鍋で残っているときに、鍋底の酸素濃度がひくいところで増殖します。
ほとんどの細菌・ウイルスは加熱で死滅しますが、ウェルシュ菌は加熱しても死滅しません!
調理中はよくまぜて鍋底に空気を送り込みましょう。
残った分は小分けして、冷蔵庫・冷凍庫に保存しましょう。

家でできる食中毒対策
鮮度と保冷
肉・魚を買うときは、とにかく鮮度をチェックしましょう。
肉の色・ドリップの状態、魚の色・形・目の輝きなどです。
ドリップが多い、ドリップがこぼれ出している商品に手を出してはいけません。
またトレー内のドリップが、ほかの食品につかないようにしましょう。
商品の温度が上がってしまわないように、最後に買うのも大切なことです。

持ち帰るときも保冷バッグ・氷・ドライアイスをじょうずに使って、短時間でサッと帰りましょう。
車や自転車につむ際も、直射日光があたったりたおれたりしないよう注意しましょう。

家についたらすぐに、冷蔵庫・冷凍庫に入れましょう。
大量買い・まとめ買いをしたものは、ここでサッと小分けにすると、ムダな解凍をせずにすみますよ。
冷蔵庫に入れておいても細菌はゆっくり増えるので、早めに食べるようにしましょう。

解凍と加熱
冷凍食品は自然解凍をさけ、かならず冷蔵庫か電子レンジでしましょう。
常温に放置することは、厳禁です。

この時にムダな解凍・冷凍をさけるために、先ほど小分け仕分けをオススメしたわけです。
とくに電子レンジ解凍の時は、ムラがないように解凍することも大切です。
肉には食中毒の原因菌がすみついていることが多いので、中心部まで75℃以上で1分以上加熱するようにしましょう。
ハンバーグやサイコロステーキなどは、とくに注意しましょう。
肉を焼いた箸と食べる時の箸も、一緒にしないようにしてください。

手洗い・流水・消毒
調理する自分の手も、しっかり洗わないといけませんね。
料理の途中でトイレに行ったり、ペットにふれたりしたら、かならず石けんで手を洗いましょう。

野菜には土にすむ病原菌がついていることがあります。
流水でしっかり洗い流しましょう。

ヘタや根元などの汚れがたまりやすいところは念入りに洗い、75℃以上のお湯に1分以上つけられるものはつけた方が安心です。
次亜塩素酸ナトリウムなどで殺菌・洗浄も効果がありますが、じゅうぶんな注意が必要です。
包丁やまな板は、菌がつきやすく落ちにくいので消毒が必要です。
家で簡単に安全にできるのは、熱湯消毒です。
80℃以上のお湯でないと意味がありません。
くれぐれも火傷には注意しましょう。

除菌洗剤やキッチンアルコールと組み合わせて、じょうずに使いましょう。
👇ココが大事!👇
冷蔵庫を過信してはいけません。できるだけその日のうちに食べきりましょう。